給与計算の内製化とは、外部に委託せず自社で給与計算業務を行うことです。
この記事では、給与計算を内製化するメリットとデメリット、そしてアウトソーシングとの比較を通じて、どちらが自社に適しているかを判断するための情報を提供します。
内製化を成功させるための具体的なポイントや、業務の詳しい内容についても解説するため、導入を検討している担当者や経営層の方はぜひ参考にしてください。
この記事の監修

日本ペイロール株式会社
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから
給与計算の内製化とは?自社で業務を行うことの基本
給与計算の内製化とは、これまで社労士事務所や代行業者といった外部の専門機関に委託していた給与計算業務を、自社の従業員が担当するように切り替えることを指します。
単に給与額を計算するだけでなく、勤怠管理から各種保険料や税金の計算、給与の振り込みまで、一連の業務内容を社内で完結させる体制を構築することが求められます。
内製化で担当する主な給与計算業務
給与計算を内製化した場合に担当する業務内容は多岐にわたります。
まず、従業員一人ひとりの労働時間や残業、休日出勤などの勤怠データを集計し、それに基づいて基本給や各種手当を含めた総支給額を算出します。
次に、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料といった社会保険料や、所得税、住民税などの税金を法律に基づいて計算し、総支給額から控除します。
最終的に、総支給額から控除額を差し引いて差引支給額(手取り額)を確定させ、給与明細を作成・配布し、指定された期日に従業員の口座へ給与を振り込みます。
その後、控除した社会保険料や税金を各機関へ納付するまでが一連の業務となります。

社労士 小栗の
アドバイス
給与計算は人事労務の「最終工程」であることを認識しましょう
給与計算業務は、単なる数字の計算ではなく、「勤怠管理」「労働条件」「社会保険・税法」といった人事労務に関する様々な要素が絡み合う、極めて複雑で重要な業務です。
内製化を検討する際には、「自社の給与体系(手当の種類、残業計算ルールなど)が法的に適正か」を事前にチェックすることが不可欠です。たとえアウトソーシングから内製化に切り替えても、元の給与体系に潜在的な問題(例えば、残業代の計算方法が間違っているなど)があれば、そのリスクを引き継いでしまうことになります。
内製化は、自社の労務管理のあり方を見直す良い機会です。給与計算を正しく行うためには、まずその前提となる労働条件や勤怠管理のルールが明確で、法律に則っているかを確認しましょう。
給与計算を内製化する3つのメリット
給与計算をアウトソーシングから内製化に切り替えることで、企業は様々なメリットを享受できる可能性があります。
具体的には、外部への委託コストを削減できる点、給与に関する情報を社内で迅速に扱えるようになる点、そして人事労務に関する専門的な知識が社内に蓄積される点などが挙げられます。
これらのメリットは、企業の状況や規模によって効果の大きさが異なります。
メリット1:コスト削減につながる可能性がある
給与計算を内製化するメリットの一つは、アウトソーシングにかかる外部委託費を削減できることです。
外部に委託する場合、基本料金に従業員数に応じた費用が加算されるのが一般的であり、従業員規模が大きい企業ほど委託費用は高額になる傾向があります。
内製化に切り替えることで、この月々のランニングコストが不要になります。
ただし、内製化にあたって給与計算システムを導入する場合は初期費用や月額利用料が発生し、担当者の人件費も考慮しなくてはなりません。
そのため、委託費用と内製化にかかる費用を総合的に比較し、費用対効果を慎重に検討することが求められます。
メリット2:迅速な給与データ修正や情報共有が可能になる
社内に給与計算の担当者がいることで、業務の柔軟性とスピードが向上する点もメリットです。
例えば、従業員の勤怠データに不備が見つかった場合や、手当の申請内容に確認が必要な場合でも、社内で直接コミュニケーションをとることで迅速に修正対応ができます。
外部に委託していると、情報のやり取りに時間がかかり、給与計算の締め切りに影響が出ることも少なくありません。
また、経営層が人件費の状況や残業時間の実績といった人事データを経営判断のために必要とした際も、担当者が社内にいればタイムリーに情報を提供でき、スピーディーな意思決定を支援します。
メリット3:社内に人事労務の専門知識が蓄積される
給与計算業務を自社で継続的に行うことは、社内に専門的なノウハウが蓄積されるというメリットをもたらします。
担当者は業務を通じて、社会保険制度や税法、労働基準法といった人事労務に関する幅広い知識を習得していきます。
これにより、従業員からの給与や保険に関する問い合わせに対して、社内で的確かつ迅速に対応できる体制が整います。
さらに、蓄積された知識や経験は、将来的に人事評価制度を見直したり、新たな福利厚生制度を導入したりする際の土台となり、企業の組織力強化にも貢献する資産となり得ます。

社労士 小栗の
アドバイス
コスト削減効果は、担当者の「時間単価」と「ミス」のリスクを含めて評価すべきです
内製化によるコスト削減効果を判断する際、単にアウトソーシング費用の有無だけでなく、内製化によって発生する「見えないコスト」も考慮に入れる必要があります。
特に重要なのは、担当者の人件費(時間単価)と業務ミスによるコストです。
担当者の人件費:給与計算にかかる実労働時間を正確に把握し、その時間を担当者の時給換算で評価してください。給与計算はミスが許されないため、チェック作業にも相応の時間がかかります。
業務ミスによるコスト:計算ミスや処理遅延は、再計算や修正作業の手間だけでなく、従業員からの信頼低下や、最悪の場合、社会保険料の納付漏れによる追徴金や延滞金といった形で企業に直接的な損失をもたらします。
内製化を検討する際は、これらのリスクとコストを総合的に判断し、アウトソーシング費用と比較して本当に「得」になるのかを慎重に見極めることが、失敗しないための鍵です。
給与計算を内製化する際に注意すべき3つのデメリット
給与計算の内製化はメリットばかりではありません。
導入を検討する際には、いくつかのデメリットや注意すべき内容を理解しておく必要があります。
特に、担当者の業務負担が増加すること、専門的な業務であるために属人化しやすいこと、そして頻繁に行われる法改正へ自社で対応し続けなければならないこと、といった課題が挙げられます。
これらのデメリットへの対策を怠ると、業務の停滞や法令違反のリスクを招く可能性があります。
デメリット1:担当者の業務負担が増加する
給与計算の内製化は、担当者の業務負担を大幅に増加させる可能性があります。
この業務は毎月決まった期間に作業が集中し、特に勤怠の締め日から給与支払日までの短いスパンで正確な処理を完了させなくてはなりません。
入社や退社、人事異動が多い時期は、手続きが複雑になり業務量がさらに増大します。
担当者が他の業務と兼務している場合、給与計算業務に時間を取られることで、本来注力すべきコア業務が圧迫される恐れがあります。
このような状況は、担当者の長時間労働を招き、業務全体の生産性を低下させる一因にもなり得ます。
デメリット2:業務の属人化を招きやすい
給与計算は専門知識を必要とするため、特定の担当者だけが業務の進め方や詳細を把握している「属人化」の状態に陥りやすいというデメリットがあります。
この状態では、もしその担当者が急な病気で休んだり、退職してしまったりした場合、業務を引き継げる人材がおらず、給与計算が滞ってしまうリスクを抱えることになります。
給与の支払いが遅延すれば、従業員の生活に直接影響を与え、会社への信頼を大きく損なう事態になりかねません。
業務内容がブラックボックス化することで、ミスや不正が発生しても周囲が気付きにくいという問題も潜んでいます。
デメリット3:法改正への対応や専門知識の習得が必要になる
給与計算に関連する法律や制度は頻繁に改正されます。
例えば、健康保険料率や厚生年金保険料率、雇用保険料率は定期的に見直され、所得税の定額減税のような臨時的な税制改正も行われます。
内製化する場合、担当者はこれらの法改正に関する情報を常に収集し、その内容を正確に理解して給与計算に反映させなくてはなりません。
最新の知識を維持するためには継続的な学習が不可欠であり、担当者にとって大きな負担となります。
もし法改正への対応が漏れたり、誤ったりすると、追徴課税や延滞金の発生といったペナルティにつながるリスクがあります。
【比較】給与計算の内製化とアウトソーシングどちらを選ぶべきか
給与計算の内製化とアウトソーシングのどちらが最適かは、企業の規模、従業員数、給与体系の複雑さ、人事部門のリソース状況によって異なります。
コスト削減やノウハウ蓄積を重視するなら内製化、業務効率化やリスク回避を優先するならアウトソーシングが有力な選択肢となるでしょう。
自社の状況とそれぞれの特徴を照らし合わせ、どちらの運用方法がより多くのメリットをもたらすか、慎重に検討することが重要です。
内製化の導入が向いている企業の特徴
給与計算の内製化は、特定の条件を持つ企業にとって効果的な選択肢となります。
例えば、従業員数が比較的少なく、正社員中心で給与体系がシンプルな企業は、計算業務の負荷がそれほど大きくないため、内製化しやすいでしょう。
また、将来的に人事労務の専門知識を社内に蓄積し、組織力の強化を図りたいと考えている企業にも適しています。
コスト意識が高く、アウトソーシングにかかる外部委託費用を削減したい場合も内製化が選択肢に入ります。
さらに、経営分析のために給与データを迅速に活用したい、あるいは従業員の個人情報を外部に出したくないといった方針を持つ企業も、内製化の導入に向いていると考えられます。
アウトソーシング(外注)の利用が向いている企業の特徴
アウトソーシングの利用は、特に業務の効率化とリスク管理を重視する企業に適しています。
従業員数が数百人規模以上の大企業や、雇用形態が多様で給与体系が複雑な企業では、給与計算業務が膨大になるため、専門業者に委託することで担当者の負担を大幅に軽減できます。
これにより、人事部門の従業員は採用活動や人材育成、制度設計といった戦略的なコア業務に集中することが可能になります。
また、頻繁な法改正への対応に不安がある場合や、担当者の退職による業務停滞リスクを避けたい企業にとっても、専門知識を持つ外部に任せることは有効な対策となります。
給与計算の内製化を成功させるためのポイント
給与計算の内製化を成功させるためには、デメリットとして挙げた課題を克服するための具体的な対策を計画的に実行することが不可欠です。
単に担当者を決めて業務を移行するだけでは、ミスや業務の停滞を招きかねません。
業務効率化のためのシステム導入、属人化を防ぐための業務標準化、そして安定した運用を実現するための体制構築という、3つのポイントを押さえて準備を進めることが求められます。
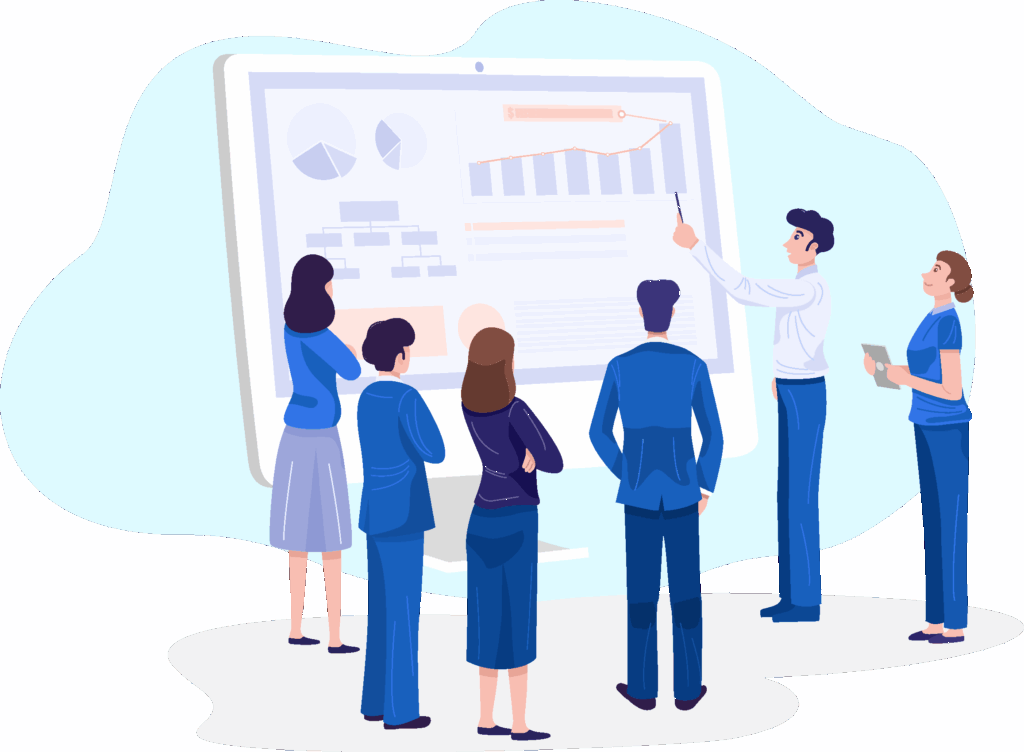
給与計算システムを導入して業務を効率化する
内製化を成功させる上で、給与計算システムの導入は極めて有効な手段です。
手作業や表計算ソフトによる管理は、計算ミスや入力漏れといったヒューマンエラーが発生しやすく、作業に多大な時間を要します。
給与計算システムを導入すれば、勤怠管理システムからデータを自動で取り込み、社会保険料や税金を自動計算することが可能です。
また、多くのシステムは法改正に自動でアップデート対応するため、担当者が自ら情報を収集し設定を変更する手間を省けます。
これにより、業務の正確性を担保しながら作業時間を大幅に短縮し、担当者の負担を軽減する効果が期待できます。
業務フローを標準化しマニュアルを作成する
業務の属人化を防ぎ、安定した運用を実現するためには、業務フローを標準化し、誰が見ても作業内容を理解できるマニュアルを作成することが重要です。
まず、毎月の給与計算に関する一連の作業手順を洗い出し、「いつ」「誰が」「何を」行うのかを明確にします。
その上で、勤怠データの集計方法、各種手当の計算ルール、イレギュラーな事態が発生した際の対応方法などを詳細に記載したマニュアルを整備します。
このマニュアルが存在することで、担当者が交代する際の引き継ぎがスムーズになるだけでなく、業務の品質を一定に保ち、ミスを未然に防ぐことにも役立ちます。
複数人で対応できる体制を構築する
給与計算業務を一人の担当者に任せきりにすると、その担当者が不在になった場合に業務が完全に停止してしまうリスクがあります。
こうした事態を避けるため、主担当者と副担当者を置くなど、複数人で業務を分担・共有できる体制を構築することが望ましいです。
複数人体制にすることで、お互いの作業内容をダブルチェックでき、計算ミスや確認漏れを防ぐ効果も期待できます。
また、一人の担当者に業務負荷が集中することを避け、負担を分散させることも可能です。
これにより、業務の継続性を確保するとともに、より正確で安定した給与計算業務の運用が実現します。
まとめ
給与計算の内製化は、外部委託コストの削減や社内へのノウハウ蓄積といったメリットがある一方で、担当者の業務負担増加や属人化のリスク、法改正への対応といった課題も伴います。
自社にとって内製化が最適な選択肢であるかを見極めるには、これらのメリットとデメリットの内容を十分に比較検討し、企業の規模やリソース、将来的な方針と照らし合わせる必要があります。
もし内製化を選択するのであれば、給与計算システムの導入による効率化、マニュアル作成による業務の標準化、そして複数人担当制によるリスク分散といった対策を計画的に講じることが、安定的な運用を実現する鍵となります。


