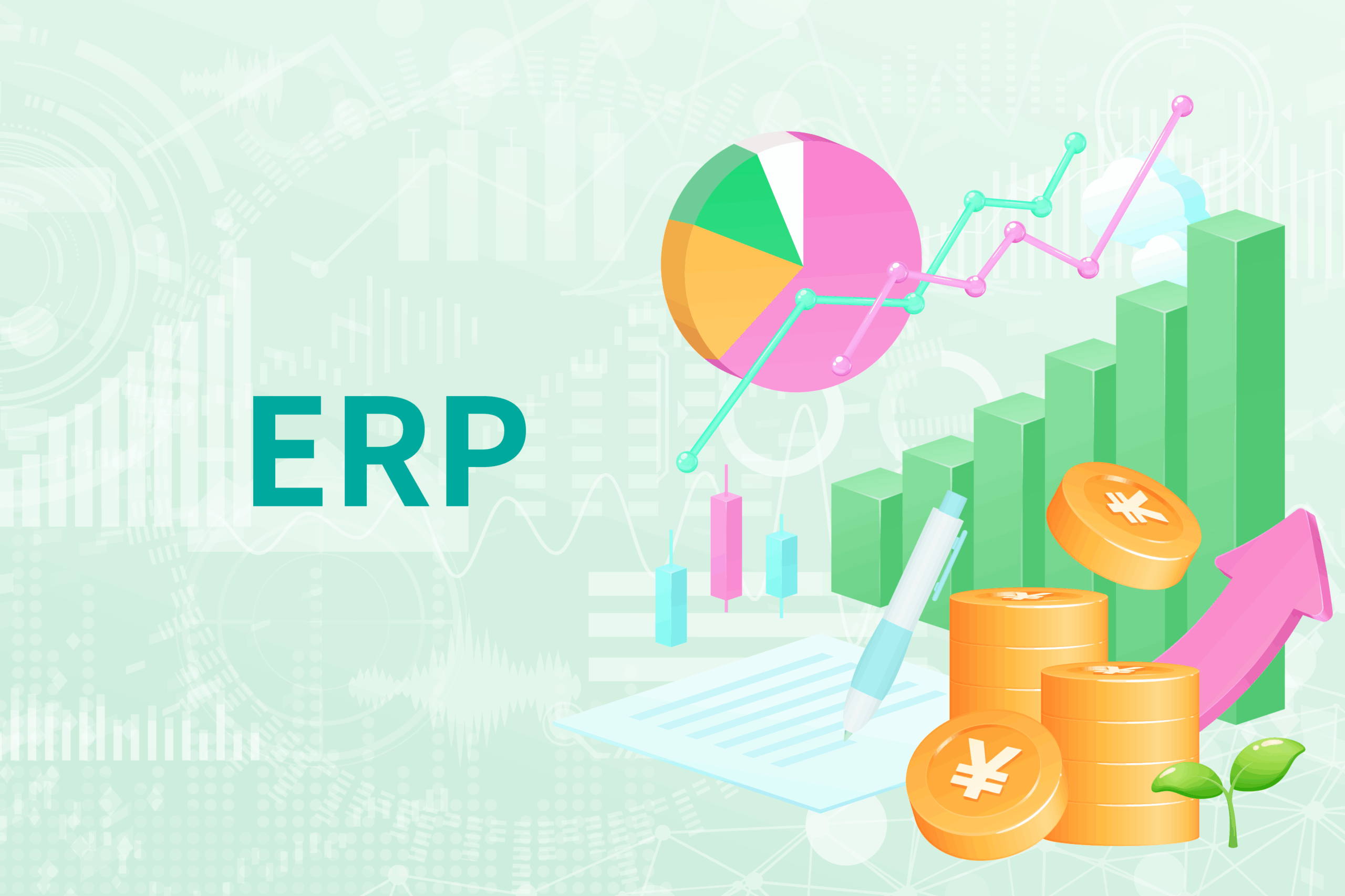【今さら聞けない!】ERPとは?基幹システムとの違いや導入のメリットをわかりやすく解説
企業の経営者、情報システム部門の担当者、業務改善に関心のあるビジネスパーソンに向けて、ERPの基本から導入のメリット・デメリットまで、ERPに関する包括的な情報についてわかりやすく解説します。ERPとは何かという基本的な概念から、基幹システムとの違い、具体的な機能、導入のメリット・デメリット、選定基準、導入プロセスまでを掘り下げていきます。
この記事の監修

日本ペイロール株式会社
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから
ERPの基本概念
ERP(Enterprise Resource Planning)とは、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を一元的に管理し、有効活用するための「考え方」や、それを実現する「システム」を指します。ERPは、企業全体の視点から資源を最適に配置し、業務プロセス全体を効率化することを目的としています。
ERPの定義と成立背景
ERPは「EnterpriseResourcePlanning」の略で、日本語では「企業資源計画」と訳されます。元々は生産管理の分野で使われていたMRP(MaterialResourcePlanning)という考え方を、企業経営全体に適用する形で発展したものです。ERPは、企業内の各部門が個別に管理していた情報を統合し、企業全体の状況をリアルタイムで把握できるようにすることを定義としています。これにより、重複入力の削減や人為的ミスの防止、迅速な意思決定を可能にしました。1973年にドイツで世界初のERPがリリースされましたが、当時のシステムは高価で導入企業は限られていました。しかし、1990年代以降のコンピュータ技術の進歩やダウンサイジング化、そして日本独自の商習慣に対応可能なERPの登場により、徐々に普及が進みました。現在では、業種・業態に合わせた多様なERPパッケージが提供されています。
部門間連携の重要性
企業活動は販売、生産、購買、会計、人事など様々な部門が連携して成り立っています。従来、これらの部門はそれぞれ独立したシステムで業務を管理しており、部門間の情報連携が難しいという課題がありました。例えば、営業部門が受けた注文情報がリアルタイムで生産部門や在庫管理部門に伝わらず、生産計画の遅れや在庫切れが発生するといった問題です。このような部門間の情報の壁は業務の非効率化や経営判断の遅れにつながります。ERPは各部門の情報を統合されたデータベースで一元管理することで部門間のスムーズな連携を実現し企業全体の業務プロセスを最適化する必要性から生まれました。これによりデータ入力の二重手間やミスを削減し常に最新の正確な情報に基づいて各部門が連携できるようになります。

社労士 小栗の
アドバイス
ERPは、人事・給与管理機能を通じて、従業員の入社から退職までの情報を一元管理できます。これにより、社会保険や雇用保険の手続きに必要な情報を正確に把握し、労務管理の効率化とコンプライアンス強化に貢献します。
基幹システムとERPの比較
基幹システムとERPは、どちらも企業の重要な業務を支えるシステムですが、その目的とカバー範囲には明確な違いがあります。基幹システムが特定の業務の効率化を目指すのに対し、ERPは企業全体の情報を統合し、経営全体の最適化を目標とします。
基幹システムの概要
基幹システムとは、企業の経営活動に不可欠な基幹業務を支援するシステムを指します。基幹業務とは、会計管理、人事給与管理、購買管理、生産管理、販売管理など、企業が事業を継続していく上で根幹となる業務のことです。これらのシステムは、通常、業務の種類ごとに独立して導入され、それぞれの業務の効率化を目的としています。例えば、製造業であれば生産管理システム、サービス業であれば顧客管理システムなど、業種によって重視される基幹システムは異なります。基幹システムは、もし停止してしまうと企業活動に大きな支障をきたすため、ミッションクリティカルシステムとも呼ばれ、その安定的稼働が不可欠です。しかし、個別の基幹システムは、それぞれが独立したデータベースを持つため、部門間のデータ連携が難しいという課題を抱えることがあります。
両者の主な相違点
基幹システムとERPの主な違いは、そのカバーする業務範囲と目的です。基幹システムは、会計、人事、受注管理といった個々の基幹業務を効率化することを目的とし、それぞれが独立して運用されることが一般的です。これに対し、ERPは企業全体の基幹業務を一つのシステムに統合し、全社的なデータの一元管理とリアルタイムでのデータ連携を目指します。これにより、部門間で発生していたデータのやり取りが不要になり、データの重複入力や多重作業を避けることが可能です。ERPが企業全体の経営資源を有効活用するための「統合基幹業務システム」と呼ばれるのは、このような違いがあるためです。したがって、基幹システムが「部分最適」を追求するのに対し、ERPは「全体最適」を実現するためのツールであるといえます。
日本におけるERPの普及
日本におけるERPの普及は、当初、海外製のERPが日本の商習慣に適合しないという課題があり、導入企業は限られていました。しかし、2000年代に入ると、日本独自の商習慣に対応したERPパッケージが多数リリースされるようになり、徐々に普及が進みました。特に、2008年のJ-SOX法(内部統制報告制度)の実施を機に、企業全体のガバナンス強化や内部統制実現のツールとしてERPが注目され、導入が進みました。J-SOX法は、上場企業とその子会社・関連会社を対象としており、経営者による内部統制の整備・評価、監査人による監査、内部統制報告書の提出などが求められます。
現在では、業種や企業規模に合わせた多様なERPパッケージが提供されており、オプションやアドオンの追加により、それぞれの企業に最適なERPを導入することが可能となっています。クラウド型ERPの登場も、初期投資を抑えたい中小企業を中心に普及を後押ししており、国内のERP市場は拡大傾向にあります。 2022年度の国内ERP市場の売上金額は1,687億円で、2027年度にはSaaS(クラウド)型がパッケージ製品の3倍以上の売上を占めると予測されています。 また、クラウド型ERPの利用率は2020年時点で45.8%に達しており、今後もクラウド化の流れは続くと見られています。
ERPの主要機能
ERPの機能は企業のあらゆる基幹業務を網羅し、経営資源の一元管理を実現します。これにより部門ごとの業務効率化だけでなく、企業全体のデータ連携を強化し、経営判断の迅速化を支援します。主な機能としては財務・会計管理、販売・顧客管理、購買・在庫管理、生産計画・管理、人事・給与管理などが挙げられます。
財務・会計管理
ERPの財務会計管理機能は、企業の資金の流れを包括的に管理し、経営状況を正確に把握するために不可欠な基本機能です。このモジュールは、総勘定元帳、売掛金管理、買掛金管理、固定資産管理、経費精算、予算管理など多岐にわたる機能を統合しています。例えば、経費精算機能では、従業員が申請した経費情報をリアルタイムで処理し、承認フローを経て自動的に会計システムに反映させることが可能です。これにより、経理部門の業務負担を大幅に軽減し、手作業によるミスを防ぎます。また、これらの会計データは企業全体の他のモジュールと連携しているため、販売データや購買データが自動的に会計情報として集約され、常に最新の財務状況を可視化できます。経営層は、リアルタイムで正確な財務諸表や経営レポートを確認できるようになり、迅速な意思決定を支援する強力なツールとなります。さらに、内部統制の強化にも繋がり、監査対応の効率化や不正防止にも貢献します。
販売・顧客管理
ERPの販売・顧客管理機能は、販売活動における一連の業務プロセスを効率化し、顧客との関係を強化するために重要な機能です。このモジュールには、受注管理、出荷管理、請求管理、売掛金管理、顧客情報管理、営業支援管理といった機能が含まれます。例えば、受注管理機能では、顧客からの注文情報をシステムに登録するだけで、リアルタイムで在庫状況を確認し、出荷指示までを自動的に連携させることが可能です。また、請求管理機能は、受注情報やサービス提供データに基づいて請求書を自動作成し、顧客への送付から入金後の消込作業までを効率化します。これにより、手作業によるミスを削減し、正確かつ円滑な販売プロセスを確立できます。さらに、顧客情報を一元管理することで、顧客の購買履歴や問い合わせ履歴を瞬時に把握し、個別のニーズに応じたきめ細やかな顧客サービスを提供できるようになり、顧客満足度の向上にも貢献します。
購買・在庫管理
ERPの購買・在庫管理機能は、企業のサプライチェーンにおける物流の効率化とコスト最適化に不可欠なモジュールです。この機能は、原材料や商品の購買、入庫、出庫、在庫の移動、廃棄といった一連のプロセスを統合的に管理します。具体的には、発注点の自動計算、仕入先管理、購買履歴の追跡、入出庫管理、棚卸し管理などが含まれます。例えば、在庫管理機能は、リアルタイムで商品の在庫状況を把握し、販売部門や生産部門が必要な情報を常に確認できるようにします。これにより、過剰在庫による保管コストの増加や、在庫不足による販売機会の損失を防ぎ、最適な在庫水準を維持することが可能です。また、購買管理機能は、過去の購買データや市場価格の情報を活用して、最適な仕入先選定や価格交渉を支援します。これらの機能が連携することで、サプライチェーン全体の透明性が向上し、調達から消費までのプロセスを効率化し、物流コストの削減と顧客サービスの向上に貢献します。
生産計画・管理
ERPの生産計画・管理機能は、主に製造業において、製品の生産活動全体を効率的に管理するための重要なモジュールです。この機能には、生産計画の立案、製造指図の管理、工程管理、資材所要量計画(MRP)、品質管理、原価管理などが含まれます。例えば、生産管理機能は、受注量や販売予測に基づいて最適な生産計画を自動で立案し、必要な原材料や部品の調達をスムーズに進めることができます。また、製造工程の進捗状況をリアルタイムで把握し、ボトルネックの特定や問題発生時の迅速な対応を可能にします。これにより、生産ラインの効率を最大化し、納期遅延のリスクを低減します。さらに、品質管理機能は、製品の品質基準を維持し、不良品の発生を抑制することで、製品の信頼性を高めます。生産計画・管理機能は、製造プロセスの全体最適化を図り、コスト削減、品質向上、納期遵守に貢献し、企業の競争力強化に寄与します。
人事・給与管理
ERPの人事・給与管理機能は、従業員の情報を一元的に管理し、人事業務全般を効率化するためのモジュールです。この機能には、従業員の基本情報、所属部署、役職、異動履歴、家族情報、通勤経路などの人事管理、勤怠管理、給与計算、社会保険・労働保険の手続き、さらにはタレントマネジメント機能などが含まれます。例えば、給与計算機能は、勤怠データに基づいて正確な給与計算を自動で行い、手作業によるミスや負担を軽減します。また、従業員のスキルや保有資格、研修の受講状況などを管理する機能を持つERP製品も多く、人材育成計画の立案や適切な人材配置に役立ちます。近年では、マイナンバー制度への対応として、マイナンバーの管理に特化した機能を提供するERP製品も増えており、厳格なセキュリティ管理のもとで個人情報を安全に取り扱うことが可能です。これらの機能により、人事業務の効率化だけでなく、従業員満足度の向上や法令遵守にも貢献します。
ERP導入の利点と課題
ERPの導入は、企業の業務効率化や経営判断の迅速化に大きなメリットをもたらしますが、一方で、初期投資の大きさや業務フローの見直しといった課題も存在します。これらの利点と課題を理解し、適切な計画を立てることが、ERP導入を成功させる鍵となります。
ERP導入のメリット
ERPの導入は企業に多岐にわたるメリットをもたらします。まず、最も大きなメリットの一つは情報の一元管理による業務効率の向上です。ERPは財務会計、販売管理、生産管理、人事管理など各部門に分散していたデータを統合データベースで一元管理することで部門間のデータ連携を容易にし情報共有のスピードを大幅に向上させます。これによりデータ入力の二重手間や重複作業が削減され人為的なミスも減少します。例えば営業活動で取引が発生した場合顧客管理システムと販売管理システムへの二重入力が不要となり無駄な工数が削減されます。また情報の一元化により常にリアルタイムで正確な情報を把握できるようになるため意思決定のスピードアップや経営状況の可視化が実現します。さらにERPの導入はガバナンスの強化にも寄与します。情報が統合されることで不正な改ざんや架空処理といった問題の抑止が可能になり管理者の目が行き届きやすくなるためセキュリティ体制も強固になります。これらのメリットは企業全体の生産性向上に繋がり競争力強化に貢献します。
業務プロセスの効率化
ERPを導入することで、これまで部門ごとに分断されていた業務プロセスが統合され、一連の流れの中で効率化されます。例えば、受注から販売、そして会計処理までの一連の業務が自動的に連携されるため、手作業や煩雑な作業が大幅に削減されます。これにより、データ入力の重複や伝達ミスを防ぎ、業務の正確性が向上します。ERPを導入する企業は、業務プロセスの自動化と効率化を図り、企業全体の生産性を高めることが可能になります。また、業務プロセスが標準化されることで、特定の個人に業務が属人化するリスクも低減され、組織全体の業務遂行能力が向上します。
情報の一元化と可視化
ERPを導入する最大のメリットの一つは、企業内のあらゆる情報の一元化と可視化が実現できることです。従来のシステムでは、各部門が個別のデータベースを保有していたため、情報が分散し、全社的なデータの統合や分析が困難でした。しかし、ERPでは共通のデータベースにすべての業務データが集約されるため、常にリアルタイムで企業の最新状況を把握することが可能になります。これにより、経営層は販売データ、在庫状況、財務状況などをリアルタイムで確認し、多角的な視点から経営状況を分析できるため、迅速かつ的確な意思決定を行うことが可能になります。また、ERPの多くにはデータ分析ツールが搭載されており、収集されたデータを活用して、より精度の高い経営戦略や戦術を立てることもできます。
経営判断の迅速化
ERPの導入は、経営層の迅速な意思決定を強力に支援します。従来の個別システムでは、経営判断に必要な情報を得るために、各部署から個別にデータを収集・集計する必要があり、多くの時間と手間がかかっていました。しかし、ERPによって財務、販売、生産、人事など、企業内のあらゆる情報が一元管理されることで、経営層はリアルタイムで企業の現状を正確に把握できるようになります。例えば、市場データの変化や営業活動の状況、在庫状況などを即座に確認できるため、勘や経験に頼ることなく、データに基づいた合理的な経営判断をタイムリーに下すことが可能になります。このように、ERPはデータドリブン経営を実現し、企業の市場価値を高める上で重要な役割を果たすのです。
コストの最適化
ERPの導入は、間接的に様々なコストの最適化に繋がります。まず、業務プロセスの効率化と自動化により、人件費の削減が見込めます。例えば、手作業によるデータ入力や書類作成の時間が短縮され、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。また、在庫管理機能の強化により、過剰在庫を抑制し、保管コストや廃棄ロスの削減が可能です。さらに、複数の個別システムをERPに統合することで、システムの運用・保守にかかるコストや、システム間のデータ連携にかかるコストを削減できる場合もあります。加えて、リアルタイムな情報に基づいて経営判断が迅速化されることで、市場機会を逃さず、ビジネスチャンスを最大限に活かすことができ、結果として売上向上にも寄与します。

社労士 小栗の
アドバイス
給与計算機能を持つERPを導入すれば、毎月の勤怠データから自動で給与が計算され、労働基準法に定められた割増賃金の計算ミスも防げます。複雑な法改正にも自動で対応してくれるため、労務担当者の負担を大幅に軽減できるでしょう。
ERP導入のデメリット
ERPの導入は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットも存在するため、導入を検討する際にはこれらの注意点を十分に理解しておく必要があります。まず、導入には比較的高額な初期投資が必要となること、そして既存の業務フローをシステムに合わせて変更する必要がある点が挙げられます。また、新しいシステムの導入は、社員にとって新しい使い方を学ぶ必要があり、教育やトレーニングが不可欠です。これらのデメリットを事前に把握し、適切な対策を講じることが、ERP導入の成功には欠かせません。
システム選定の複雑さ
ERPシステムは多種多様なベンダーから提供されており、機能や価格帯も大きく異なります。そのため、自社に最適なシステムを選定することは非常に複雑で難しい作業となります。選定にあたっては、まず自社の現状の課題やニーズを明確にし、ERP導入によって解決したい具体的な目的を詳細に洗い出す必要があります。例えば、製造業向けのERPとサービス業向けのERPでは搭載されている機能が異なるため、自社の業種や事業規模に合った機能が十分に備わっているかを確認することが重要です。また、導入形態(クラウド型かオンプレミス型か)や、将来的な拡張性、他のシステムとの連携性なども考慮する必要があります。これらの要素を総合的に評価し、複数の製品を比較検討する手間がかかることが、システム選定における大きなデメリットとなります。
社内トレーニングの必要性
ERPシステムは、企業の基幹業務を一元的に管理する性質上、多くの従業員が日常的に利用することになります。そのため、新しいシステムの使い方を従業員が習熟するための社内トレーニングは不可欠です。ERPの導入は、従来の業務フローの変更を伴うことが多く、新しいシステムに慣れるまでに時間と労力がかかります。十分なトレーニングが行われない場合、従業員がシステムをうまく使いこなせず、かえって業務効率が低下したり、システムが形骸化してしまうリスクがあります。従業員が新しいシステムを抵抗なく受け入れ、最大限に活用できるよう、導入前から計画的な教育プログラムを策定し、継続的なサポート体制を構築することが重要です。
初期投資と維持費用
ERPシステムの導入には比較的高額な初期投資と継続的な維持費用が発生します。特にオンプレミス型ERPの場合、サーバーやネットワーク機器などのハードウェア購入費用、ソフトウェアのライセンス費用、導入コンサルティング費用、カスタマイズ費用などが初期費用として数百万円から数千万円単位でかかることがあります。また、導入後もシステムの運用・保守費用、定期的なバージョンアップ費用、そしてシステムを管理するための人件費といった継続的なコストが発生します。クラウド型ERPであれば、初期費用を抑えられることが多いですが、月額または年額の利用料金が発生し、長期的に見るとコストがかさむ可能性もあります。導入前に費用対効果を慎重に見極め、予算計画を立てることが重要となります。
既存業務フローの変更
ERPシステムの導入は、企業の業務プロセス全体を効率化することを目的としているため、既存の業務フローの大幅な変更を伴うことが高確率で発生します。これは、ERPが持つ標準的な業務プロセスに自社の業務を合わせる「FittoStandard」という考え方が推奨されるためです。従業員は長年慣れ親しんだ業務のやり方を変える必要があり、これに対する抵抗や混乱が生じる可能性があります。例えば、これまで手作業で行っていた業務がシステム化されたり、複数の部署で行っていた作業が一つの部署に集約されたりすることで、従業員は新しい使い方を覚え、新しい役割に適応しなければなりません。このような変更を従業員に十分に周知し、理解と協力を得ることが、ERP導入を成功させる上で重要な注意点となります。適切な社内調整と段階的な導入計画が不可欠です。
ERPの進化と導入形態
ERPは、その誕生から現在に至るまで、IT技術の進歩とともに進化を遂げてきました。特に、近年ではクラウド技術の発展により、導入形態の選択肢が多様化しており、企業のニーズに合わせた柔軟なシステム導入が可能になっています。
ERPの発展経緯
ERPの概念は、1970年代の生産管理手法であるMRP(Material Resource Planning)から発展し、1973年にドイツのSAP社が世界初のERPをリリースしました。当時の情報システムは、財務会計、販売管理、生産管理、人事給与といった各部門で個別に開発され、それぞれが独立したシステムとして使われていました。しかし、部門間のデータ連携が非常に難しく、情報の分断が課題となっていました。ERPは、当初から複数の部門別システムを統合し、分散していたマスターデータやデータベースを一箇所に集約することで、各システムが連動して動くように設計された画期的なパッケージシステムでした。その後、1990年代に入ると、コンピュータのダウンサイジング化が進み、メインフレームからクライアントサーバー型への移行が進んだことで、ERPの導入は急速に普及しました。2000年代以降は、インターネット技術の発展とクラウドコンピューティングの登場により、ERPはさらなる進化を遂げ、企業のIT戦略の中核を担う存在として広範な業界で導入されるようになりました。
クラウド型ERPの登場
近年、インターネット環境を利用して提供されるクラウド型ERPが登場し、その導入が加速しています。クラウド型ERPは、自社でサーバーなどのインフラを保有・管理する必要がなく、ベンダーのクラウドサーバー上でシステムを利用する形態です。この導入形態の大きなメリットは、初期導入費用を抑えられる点にあります。従来のオンプレミス型に比べて、ハードウェアの購入やシステム構築にかかるコストが削減され、ライセンス費用も月額制や年額制で支払うことが多いため、費用負担が軽減されます。また、インターネットに接続できる環境があれば、場所を問わずにシステムにアクセスできるため、リモートワークや多拠点展開にも柔軟に対応できます。運用・保守もベンダー側が行うため、社内のITリソースを削減できるという利点もあります。一方で、カスタマイズの自由度がオンプレミス型に比べて低い場合がある点や、データが外部サーバーに保存されるためセキュリティに対する懸念が生じる可能性もあります。しかし、多くのクラウドベンダーは強固なセキュリティ対策を講じており、企業は信頼できるベンダーを選定することが重要です。
オンプレミス型ERPの特性
オンプレミス型ERPは、企業が自社内にサーバーやネットワーク機器などのITインフラを構築し、その上にERPシステムを導入・運用する形態です。この方式の最大の特性は、システムに対する高い自由度とカスタマイズ性です。自社の複雑な業務プロセスや独自の商習慣に合わせて、システムを細かく設計・変更できるため、既存の業務フローを大きく変えることなく導入を進めたい企業や、特殊な要件を持つ企業に適しています。また、すべてのデータが自社内のネットワーク環境で管理されるため、セキュリティ面での安心感が高いと感じる企業も多いでしょう。しかし、オンプレミス型ERPは、初期導入費用が高額になる傾向があります。サーバーやネットワーク機器の購入、システムの構築、ソフトウェアライセンスの取得など、多額の投資が必要です。さらに、導入後もシステムの運用・保守、セキュリティ対策、バージョンアップなどを自社のIT部門が担当する必要があり、専門知識を持つ人材や継続的な運用コストが必要となります。導入期間も比較的長くなる傾向があるため、企業の規模やITリソースを考慮した上で慎重に検討する必要があります。

社労士 小栗の
アドバイス
給与計算機能を持つERPを導入すれば、毎月の勤怠データから自動で給与が計算され、労働基準法に定められた割増賃金の計算ミスも防げます。複雑な法改正にも自動で対応してくれるため、労務担当者の負担を大幅に軽減できるでしょう。
ERPパッケージの選定基準
ERPパッケージの選定は、企業の将来を左右する重要な経営判断です。多種多様なERPの中から自社に最適なシステムを選び出すためには、機能面だけでなく、導入形態やサポート体制、セキュリティ、そして将来的な拡張性まで、多角的な視点から検討することが不可欠です。ここでは、具体的な選定基準を解説します。
自社要件との適合性
ERPパッケージを選定する上で最も重要な基準の一つが、自社のビジネス要件との適合性です。ERPは企業の基幹業務を網羅するシステムであるため、自社の業種や事業規模、特有の業務プロセスに合致しているかを確認することが不可欠です。まず、現状の業務課題を詳細に洗い出し、ERP導入によって何を解決したいのかという目的を明確にしましょう。その上で、候補となるERPシステムが、これらの課題を解決するための機能や柔軟性を持っているかを評価します。例えば、製造業であれば生産管理機能の充実度、サービス業であれば顧客管理機能の柔軟性などが重要な検討ポイントとなります。また、導入後の業務フローをどのように変更するのか、システムに合わせる部分とカスタマイズが必要な部分を明確にする「フィット&ギャップ分析」を行うことで、より精度の高い適合性を判断できます。業務に合わないシステムを導入してしまうと、かえって業務効率が低下したり、追加開発によるコストが増大したりするリスクがあるため、慎重な検討が求められます。
システムの提供方式
ERPシステムの提供方式は、大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」に分けられ、それぞれの特性が選定基準となります。クラウド型ERPは、インターネット経由でベンダーが提供するシステムを利用する方式で、自社でサーバーなどのインフラを構築・運用する必要がないため、初期費用を抑えやすく、短期間での導入が可能です。また、運用・保守はベンダー側が行うため、社内のITリソース負担を軽減したい企業や、リモートワークを推進したい企業に適しています。一方、オンプレミス型ERPは、自社内にサーバーを設置し、システムを構築・運用する方式で、カスタマイズの自由度が高く、自社の独自の業務要件に細かく合わせたい企業に向いています。しかし、初期費用が高額になり、システム管理に専門知識を持つ人材が必要となります。どちらのシステム提供方式が自社に適しているかは、予算、導入期間、カスタマイズの必要性、ITリソースの状況などを総合的に考慮して検討することが重要です。
システムの安定稼働
ERPシステムは企業の基幹業務を支えるため、その安定稼働は極めて重要な選定基準です。システムが頻繁に停止したり、処理速度が遅かったりすると、業務に大きな支障をきたし、経営活動そのものが停止するリスクも生じます。選定時には、システムの稼働実績や信頼性、提供ベンダーのサポート体制を十分に確認する必要があります。特に、災害発生時や予期せぬトラブル発生時の復旧体制(ディザスターリカバリー)がどのように整備されているか、データのバックアップ体制はどうなっているかなどを確認しましょう。また、システムの負荷テストの結果や、ピーク時のパフォーマンスに関する情報も重要な判断材料となります。ベンダーが提供するSLA(サービスレベル合意書)の内容を精査し、万が一のシステム障害時にどのような対応が期待できるかを把握しておくことも大切です。安定稼働は、日々の業務効率だけでなく、企業の信頼性や事業継続性にも直結するため、非常に重視すべきポイントとなります。
将来的な拡張性
ERPシステムを選定する際には、現在の業務要件だけでなく、将来的なビジネスの成長や変化に対応できる拡張性があるかどうかが重要な判断基準となります。企業は常に変化しており、事業拡大や新規事業の立ち上げ、組織改編などによって、新たな機能や連携が必要になることがあります。拡張性の高いERPは、必要に応じてモジュールを追加したり、他のシステムと容易に連携したりできる柔軟性を持っています。例えば、ユーザー数の増加や取引量の増大に対して、システムのリソースを柔軟に拡張できるクラウド型ERPは、成長企業にとって特に有利な選択肢となり得ます。また、カスタマイズの容易さも拡張性の一部として考慮すべきです。独自のビジネスプロセスに対応するためのアドオン開発がスムーズに行えるか、将来的な機能追加や変更が容易な構造になっているかを確認することで、長期的な視点でのシステム活用が可能になります。
操作のしやすさ
ERPシステムは、企業の多くの従業員が日常的に利用するため、操作のしやすさは非常に重要な選定基準となります。たとえ高機能なシステムであっても、従業員が使いこなせない場合、業務効率の低下や導入後の定着率の悪化につながる可能性があります。直感的で分かりやすいユーザーインターフェース(UI)や、迷わずに操作できるユーザーエクスペリエンス(UX)が備わっているかを確認しましょう。例えば、画面のレイアウト、メニュー構造、データの入力方法などがシンプルで、初めて利用する従業員でもすぐに使い方を習得できるようなシステムが理想的です。試用期間を設けたり、デモンストレーションを通じて実際の操作性を確認したりすることで、導入後のギャップを減らすことができます。従業員の視点に立ち、日常業務での利用を想定した上で、操作性を評価することが成功への鍵となります。
導入後のサポート体制
ERPシステムは、導入して終わりではなく、導入後の運用・保守、トラブル対応、機能追加、従業員の教育など、長期的なサポートが不可欠です。そのため、ベンダーのサポート体制が充実しているかどうかも重要な選定基準となります。具体的には、システムの導入支援から、運用中の技術的な問い合わせへの対応、定期的なシステムアップデート、障害発生時の迅速な復旧対応などが挙げられます。特に、初めてERPを導入する企業や、社内にIT専門人材が不足している企業にとっては、国内でのサポートが充実しているベンダーを選ぶことが推奨されます。コンサルティングサービスを提供しているベンダーであれば、導入計画の策定から業務フローの見直し、従業員へのトレーニングまで、幅広い支援を期待できます。導入後の手厚いサポートは、システムの安定稼働と最大限の活用を保証するために不可欠であり、ベンダーの導入実績や顧客満足度も参考にしながら、信頼できるパートナーを選びましょう。
セキュリティ対策
ERPシステムは、企業の財務情報、顧客データ、人事情報など、機密性の高いあらゆる情報を一元的に管理するため、強固なセキュリティ対策が不可欠です。情報漏洩やサイバー攻撃のリスクから企業を守るため、選定時には以下の点を重点的に確認しましょう。まず、データの暗号化、ユーザー認証機能、アクセス権限の細かな設定、ログ管理機能など、ERPシステム自体にどのようなセキュリティ機能が搭載されているかを確認します。特にクラウド型ERPの場合、データが外部サーバーに保存されるため、ベンダーのセキュリティ体制やデータセンターの物理的セキュリティ、災害対策、プライバシーポリシーなどを詳細に確認し、信頼できるベンダーを選ぶことが重要です。また、定期的なセキュリティ監査や脆弱性診断の実施状況、万が一セキュリティインシデントが発生した場合の対応フローなども確認することで、リスクを最小限に抑えることができます。システム全体のセキュリティを確保することは、企業の信頼性を維持し、事業継続性を確保するために欠かせません。
導入実績の確認
ERPパッケージを選定する際には、導入を検討しているベンダーや製品の導入実績を十分に確認することが重要です。特に、自社と類似の業種や事業規模の企業での導入成功事例があるかどうかは、重要な判断材料となります。類似企業での実績が豊富であれば、そのERPシステムが自社の業務にある程度フィットする可能性が高く、導入後のミスマッチのリスクを低減できます。また、過去の導入事例を通じて、ベンダーの専門知識や、特定の業界に特化したノウハウ、導入プロジェクトの遂行能力などを把握することができます。ベンダーの公式サイトやIR情報、または直接問い合わせて導入実績の詳細や顧客からの満足度を確認しましょう。成功事例だけでなく、失敗事例やその原因、対処法についても情報収集することで、自社の導入計画に活かすことができます。
ERP導入時の留意点
ERP導入は単なるシステム導入に留まらず、企業全体の業務プロセスや組織体制に大きな影響を与えるプロジェクトです。そのため、導入を成功させるためには、明確な目的設定、適切なプロジェクトチームの編成、既存業務の徹底的な再評価と新業務フローの設計、既存システムとの連携など、多岐にわたる留意点が存在します。
導入目的の明確化
ERPを導入する際の最初の、そして最も重要な留意点は、導入目的を明確にすることです。何のためにERPを導入するのか、ERPを導入することでどのような課題を解決し、どのような成果を期待するのかを具体的に定義する必要があります。例えば、「業務プロセスの効率化」「コスト削減」「情報の一元化と可視化」「内部統制の強化」「経営判断の迅速化」など、具体的な目標を設定しましょう。導入目的が曖昧なままだと、システム選定が難航したり、導入後に期待通りの効果が得られなかったりする可能性があります。プロジェクトメンバー全員で導入目的を共有し、共通認識を持つことで、その後の要件定義やシステム選定、導入プロセス全体を通して方向性がぶれることなく進められます。定量的な目標(例:リードタイム〇〇%短縮、在庫〇〇%削減)と、定性的な目標(例:品質改善、SCM構築)の両面から検討することが推奨されます。
プロジェクトチームの編成
ERP導入を成功させるためには、適切なプロジェクトチームの編成が不可欠です。プロジェクトチームは、情報システム部門の担当者だけでなく、経営層、そして実際にシステムを利用する各業務部門のキーマンを巻き込むことが重要です。経営層の参画は、導入目的の明確化や意思決定の迅速化に寄与し、プロジェクト全体の方向性を示す上で不可欠です。業務部門の担当者は、現状の業務フローや課題、具体的な業務要件を最もよく理解しているため、要件定義や新業務フローの設計において中心的な役割を担います。また、外部のERP導入コンサルタントを招き、専門的な知見や豊富な経験を活用することも有効です。コンサルタントは、中立的な立場からプロジェクト全体の推進を支援し、ベンダー選定から導入後の定着まで、様々な局面で貴重なアドバイスを提供します。強力なリーダーシップと各部門の協力体制が整ったプロジェクトチームを編成することで、複雑なERP導入プロジェクトを円滑に進めることが可能になります。
既存業務の再評価
ERP導入は、既存の業務フローをシステムに合わせて変更する機会となるため、現状の業務を徹底的に再評価することが重要な留意点です。これは、単に現在の業務をそのままシステムに移行するのではなく、非効率な部分や無駄なプロセスがないかを見直し、改善の機会として捉えることを意味します。例えば、長年の慣習で続けられてきた業務や、特定の個人に属人化している業務など、ERP導入を機に標準化・効率化できる部分がないか検討します。現場の担当者へのヒアリングを通じて、業務の実態や課題を詳細に洗い出し、解決すべき優先順位をつけましょう。この再評価のプロセスは、「フィット&ギャップ分析」とも呼ばれ、ERPの標準機能に合わせる「FittoStandard」の考え方に基づいて、業務を変更する部分とシステムをカスタマイズする部分を明確にするために行われます。既存業務の課題を解消し、ERPの機能を最大限に活用するためには、この再評価が不可欠です。
新業務フローの設計
既存業務の再評価が完了したら、ERP導入後の新しい業務フローを設計することが重要です。ERPは、企業全体の業務プロセスを統合し、効率化を目指すシステムであるため、システム導入に合わせて業務フローも最適化する必要があります。この際、ERPの標準機能を最大限に活用し、無駄を排除した効率的なプロセスを設計することが重要です。例えば、リーン管理の原則を取り入れ、効率性と価値を最大化するアプローチを適用することも有効です。新しい業務フローの設計には、業務に精通した各部門の担当者が深く関与し、現場の意見を反映させることが不可欠です。また、新業務フローが従業員に受け入れられ、定着するためには、変更される業務について関係する部署にしっかりと周知し、合意を得る必要があります。新しい業務フローを明確にすることで、ERPシステム導入後の運用をスムーズにし、期待する効果を最大限に引き出すことが可能になります。
既存システムとの連携
ERPを導入する際、既存のシステムが複数存在する場合、それらとの連携は重要な留意点となります。企業によっては、ERPですべてのシステムを置き換えるのではなく、既存の特定のシステム(例えば、レガシーシステムや特定の専門業務システム)を引き続き利用したいと考える場合があります。その際、ERPと既存システムとの間でスムーズなデータ連携が可能であるかを確認する必要があります。データ連携がうまくいかない場合、情報の分断や重複入力が発生し、ERP導入のメリットが十分に活かせない可能性があります。データ連携の方法としては、API連携、ファイル連携、データベース連携など様々な方法があります。ベンダーの提供する連携ツールや、外部のデータ連携ソリューションの活用も検討し、システム変更時の影響を最小限に抑え、運用コストの削減を図ることが重要です。既存システムとの連携を円滑にすることで、情報システムの強化や業務の効率化をより確実に図ることができます。
ERP導入のプロセス
ERP導入は、企業の根幹を担う重要なプロジェクトであり、その成功は周到な計画と段階的なプロセスにかかっています。導入目標設定からプロジェクトチーム発足、現行業務分析、新業務フロー策定、システム選定、試験運用、そして本稼働への移行まで、各フェーズを丁寧に進めることが不可欠です。
導入目標の設定
ERP導入のプロセスにおいて、最初のステップとして最も重要なのが、導入目標の明確な設定です。この段階では、単に「業務効率化」といった抽象的な目標ではなく、中長期的な経営戦略と現状の課題を照らし合わせながら、ERPを導入することで達成したい具体的な成果を定義します。例えば、「リードタイムを〇〇%短縮する」「在庫を〇〇%削減する」「調達価格を〇〇%低下させる」といった定量的な目標や、「サプライチェーン全体の可視化」「内部統制の強化」といった定性的な目標を設定します。この目標設定は、プロジェクト全体の方向性を決定づける羅針盤となり、その後の要件定義やシステム選定、導入効果の評価基準にも影響します。プロジェクトメンバー全員が共通の認識を持ち、目標達成に向けて一丸となって取り組めるよう、慎重かつ具体的に目標を定めることがERP導入成功の鍵となります。
プロジェクトチームの発足
ERP導入プロジェクトを円滑に進めるためには、適切なプロジェクトチームの発足が不可欠です。このチームは、ERP導入の専門知識を持つメンバーだけでなく、経営層、そして実際にシステムを利用する各業務部門のキーパーソンを含めることが重要です。経営層の参加は、プロジェクトの推進力となり、意思決定を迅速化します。各業務部門の代表者は、現行業務の深い知識を持ち、新業務フローの設計やシステムへの要件定義において中心的な役割を担います。また、外部のERP導入コンサルタントの活用も非常に有効です。コンサルタントは、豊富な経験と専門知識に基づいて、プロジェクト計画の策定、ベンダー選定の支援、業務フローの見直し、課題解決の提案など、多岐にわたるサポートを提供します。強固なリーダーシップと部門間の連携、そして専門家のアドバイスが一体となったプロジェクトチームを編成することで、複雑なERP導入を成功に導くことができます。
現行業務の分析
ERP導入のプロセスにおいて、導入目標の設定とプロジェクトチームの発足に続いて重要なのが、現行業務の徹底的な分析です。この段階では、企業の現状の業務フローを詳細に把握し、非効率な点、ボトルネック、重複作業、属人化している業務などを洗い出します。各部門の担当者へのヒアリングや業務プロセスの可視化を通じて、データ入力の方法、情報の流れ、承認プロセスなどを細かく確認します。この分析は、ERPの導入によって解決すべき具体的な課題を明確にし、新しい業務フローを設計するための基礎となります。また、現行業務の分析を通じて、ERPの標準機能で対応できる部分と、カスタマイズや業務フローの変更が必要な部分を識別する「フィット&ギャップ分析」を行います。これにより、システム導入後のミスマッチを防ぎ、不要なカスタマイズを削減して、導入コストや期間の最適化を図ることができます。
新業務フローの策定
現行業務の分析と課題の洗い出しが完了したら、次にERP導入後の新しい業務フローを策定します。このステップは、単に既存の業務をシステムに置き換えるだけでなく、ERPの機能を最大限に活用し、企業全体の業務プロセスを最適化することを目的とします。新しい業務フローを設計する際には、ERPシステムが提供する標準的なプロセスを参考にしつつ、自社の特性に合わせて柔軟に対応することが求められます。例えば、自動化できる部分は積極的にシステムに任せ、これまで手作業で行っていた業務を効率化します。このフェーズでは、各業務部門の担当者が中心となり、システム部門や外部コンサルタントと連携しながら、現実的かつ効果的な業務フローを策定します。策定した業務フローは文書化し、関係者間で共有することで、導入後の混乱を防ぎ、従業員が新しい業務にスムーズに適応できるようになります。
システム選定の実施
新業務フローの策定が完了したら、次にいよいよERPシステムの選定を実施します。この段階では、これまでに明確にした導入目的、要件、そして策定した新業務フローに最も適合するシステムを選び出すことが重要です。市場には多数のERPパッケージが存在し、それぞれ機能、価格、提供形態(クラウド型かオンプレミス型か)、ベンダーのサポート体制などが異なります。複数の候補製品を比較検討し、自社の要件をどれだけ満たしているかを評価します。機能面だけでなく、将来的な拡張性、操作性、セキュリティ対策、そして導入後のサポート体制なども重要な検討ポイントとなります。ベンダーからの提案内容を詳細に精査し、必要に応じてデモンストレーションや既存ユーザーへのヒアリングも行い、多角的な視点から総合的に評価することで、自社に最適なERPシステムを選定することができます。
試験的な運用
システム選定後、本格的な稼働に移行する前に、試験的な運用(パイロット運用やテスト運用とも呼ばれます)を実施することが重要です。この段階では、例えば、限定された部署や特定の業務範囲でERPシステムを実際に使用し、導入計画通りにシステムが機能するか、業務フローがスムーズに流れるかなどを検証します。テストデータを用いて、入力、処理、出力の一連の流れを確認し、エラーが発生しないか、期待通りの結果が得られるかなどを綿密にチェックします。また、現場の従業員がシステムを実際に操作することで、操作性や使い勝手に関するフィードバックを収集し、改善点や課題を特定します。この試験運用を通じて、システムの問題点を事前に洗い出し、修正することで、本稼働後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな移行を実現できます。同時に、従業員のシステム習熟度を高め、新しい業務プロセスへの理解を深める機会ともなります。
本稼働への移行
試験的な運用で問題点が解消され、従業員のシステム習熟度も高まった段階で、いよいよERPシステムの本稼働へと移行します。このフェーズは、ERPを導入するプロジェクトの最終段階であり、企業全体が新しいシステムと業務プロセスに切り替わる重要な局面です。本稼働では、実際の業務データをシステムに投入し、全社的に新しいERPシステムを運用開始します。移行時には、旧システムからのデータ移行、マスターデータの最終確認、従業員への最終的なトレーニングとサポート体制の確立が重要となります。また、本稼働後も、予期せぬトラブルが発生する可能性があるため、迅速に対応できる運用・保守体制を整備しておくことが不可欠です。定期的な効果測定を行い、ERP導入によって設定した目標が達成されているかを確認し、必要に応じてシステムの調整や業務プロセスの改善を継続的に行うことで、ERP導入のメリットを最大限に享受することができます。
まとめ
ERPは企業全体の経営資源を一元管理し業務プロセスを最適化するための強力なツールです。基幹システムが個々の業務を効率化するのに対しERPは企業全体の情報統合と経営判断の迅速化を目指します。導入には初期投資や業務フローの変更といった課題も伴いますが情報の一元化による業務効率化データ可視化による迅速な経営判断コスト最適化などのメリットは計り知れません。クラウド型ERPの登場により中小企業でも導入しやすくなりました。ERP選定では自社要件との適合性システムの提供方式安定性拡張性操作性サポート体制セキュリティそして導入実績を総合的に評価することが重要です。導入プロセスにおいては明確な目標設定適切なプロジェクトチームの編成現行業務の再評価と新業務フローの設計既存システムとの連携を綿密に進めることが成功の鍵となります。これらの点を踏まえERPの導入は企業の持続的な成長と競争力強化に貢献するでしょう。