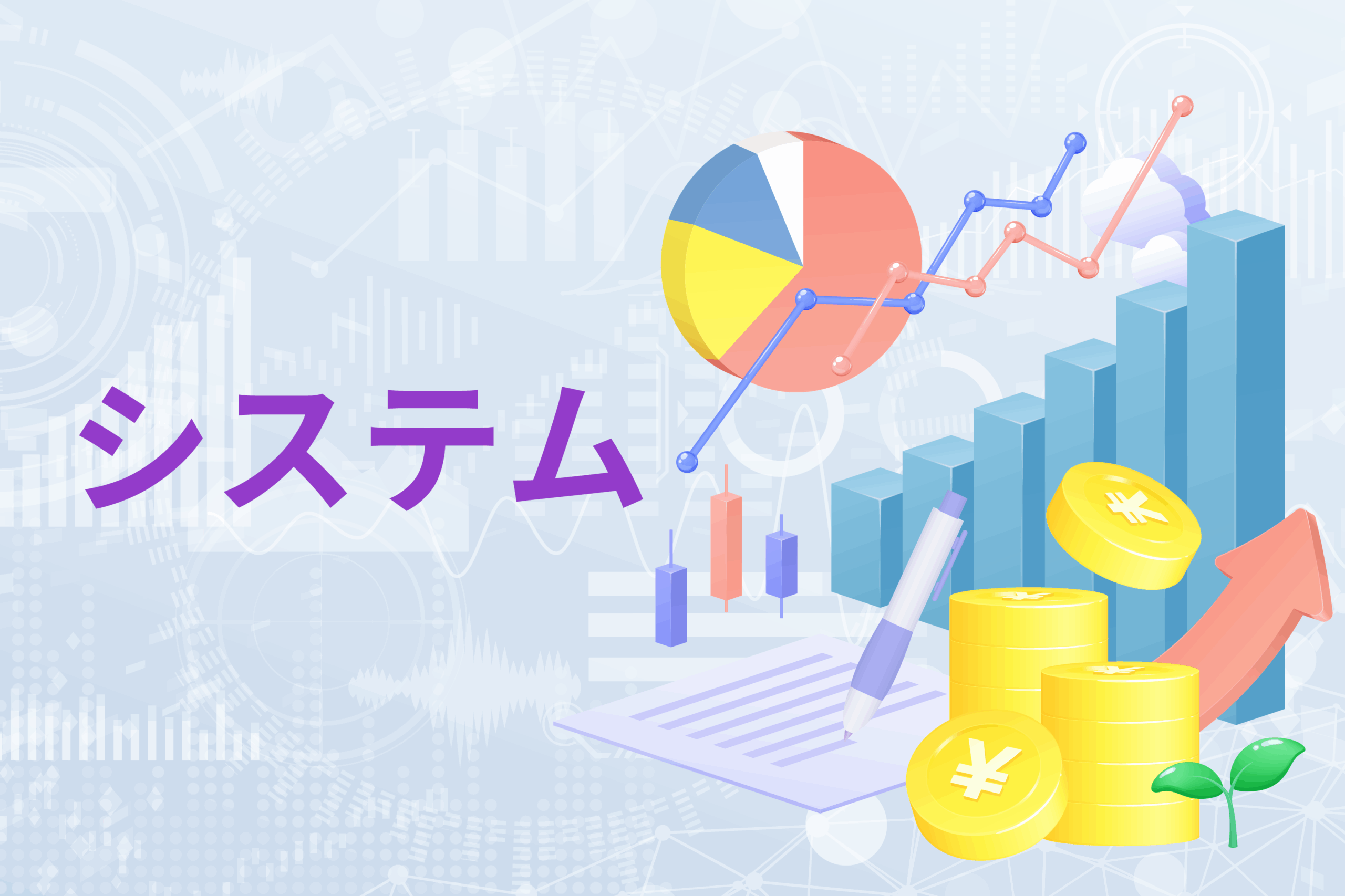奉行クラウド導入のメリットは?料金・機能を比較し失敗しない選び方
奉行クラウドは、中小企業の経理や人事労務といったバックオフィス業務の効率化を実現するクラウドサービスです。
本記事では、奉行クラウドを導入するメリットや注意点、主要製品の機能と料金プランを比較し、自社に最適な製品を選ぶためのポイントを解説します。
スムーズな導入には、専門家によるセットアップや導入指導といった導入支援サービスの活用も有効な手段となります。
この記事の監修

日本ペイロール株式会社
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから
奉行クラウドとは?従来の奉行シリーズとの違いを解説
奉行クラウドは、株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)が提供するクラウド型の基幹業務システムです。
従来のインストールが必要なパッケージ版(オンプレミス版)とは異なり、自社でサーバーを構築・管理する必要がありません。
インターネット環境とPCさえあれば、契約後すぐに利用開始できる手軽さが大きな特徴です。
データはクラウド上で一元管理され、法改正への自動アップデートや、場所を問わない柔軟な働き方を支援します。
奉行クラウドを導入して得られる5つのメリット
奉行クラウドの導入は、業務効率化やコスト削減に直結する多くのメリットをもたらします。
場所や時間を選ばずに業務を行える柔軟性や、法改正への自動対応、専門家とのスムーズなデータ連携など、バックオフィス部門の生産性を大きく向上させることが可能です。
また、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するツールとして、導入時にIT導入補助金などの制度を活用できる場合もあります。
メリット1:いつでもどこでも最新のデータを共有できる
奉行クラウドはインターネット環境があれば、オフィスだけでなく自宅や外出先など、場所を問わずにシステムへアクセスできます。
これによりテレワークやワーケーションといった多様な働き方に柔軟に対応可能です。
データはクラウドサーバーで一元管理されるため、全部署の担当者や経営層が常に最新の情報を共有でき、迅速な意思決定を支援します。
多くの企業での導入実績が、その利便性と信頼性を裏付けています。
複数拠点を持つ企業においても、リアルタイムでの情報連携が実現し、業務の分断を防ぎます。
メリット2:システムの運用や管理にかかる手間を削減できる
従来のパッケージ版ソフトウェアでは、自社でサーバーを設置し、データのバックアップやOSのアップデート、セキュリティ対策といった管理業務を情報システム担当者が行う必要がありました。
しかし奉行クラウドでは、これらのサーバー運用・保守管理はすべて提供元であるOBCが行います。
そのため、企業側の運用負荷が大幅に軽減され、情報システム担当者はより戦略的なIT活用など、本来のコア業務に専念できるようになります。
これにより、人件費を含めた見えないコストの削減にも貢献します。
メリット3:専門家との連携がスムーズになり業務が効率化する
奉行クラウドには、顧問の会計事務所や社会保険労務士などが無料で利用できる「専門家ライセンス」が標準で付属しています。
これにより、専門家は企業と同じデータをリアルタイムで直接閲覧・操作できるようになります。
従来のように、データをメールで送受信したり、書類を郵送したりする手間が一切不要となり、月次決算の早期化や労務相談が格段にスムーズになります。
専門家からの的確なアドバイスを迅速に受けられる体制が整い、経営判断の質を高めることにもつながります。

社労士 小栗の
アドバイス
専門家ライセンスの活用は、人事労務部門にとって大きなメリットです。社会保険手続きや給与計算で不明な点があった際に、顧問の社労士がシステム上で直接確認・修正できるため、業務の正確性が向上し、コンプライアンスリスクを低減できます。
メリット4:法改正やビジネス環境の変化に自動で対応できる
経理や労務の分野では、毎年のように税制改正や社会保険料率の変更が行われます。
奉行クラウドは、こうした法改正や制度変更に対応するためのプログラム更新が自動で行われるため、利用者は常に最新の法令に準拠した状態でシステムを使い続けることができます。
インボイス制度や電子帳簿保存法といった大きな制度変更にも迅速に対応し、企業がコンプライアンスを遵守した上で業務を遂行できるよう支援します。
手動での更新作業が不要になるため、対応漏れのリスクをなくし、担当者の負担を軽減します。
メリット5:サーバーなどの設備投資が不要になりコストを抑制できる
オンプレミス型のシステムを導入する場合、サーバー機器の購入や設置、関連ソフトウェアのライセンス費用など、多額の初期投資が必要でした。また、数年ごとには機器の入れ替えも発生します。
奉行クラウドは月額または年額の利用料を支払うサブスクリプションモデルであるため、これらの設備投資が一切不要です。初期費用を大幅に抑えられるだけでなく、サーバーの維持管理費やリプレイスコストもかからないため、長期的な視点で見た総所有コスト(TCO)の削減につながります。
奉行クラウド導入前に確認すべき2つの注意点
奉行クラウドは業務効率化に大きく貢献する一方、導入を決定する前に把握しておくべき注意点も存在します。
特に、サービスの根幹であるインターネット接続への依存度や、従来のオンプレミス版と比較した際のカスタマイズ性の違いについては、自社の業務環境や運用方針と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。
これらの点を理解しておくことで、導入後のミスマッチを防ぐことができます。
注意点1:インターネット環境がなければ利用できない
奉行クラウドは、すべての機能がインターネットを介して提供されるクラウドサービスです。
そのため、安定したインターネット接続環境がなければシステムにアクセスできず、業務が完全に停止してしまうリスクがあります。
オフィスのメイン回線に通信障害が発生した場合や、災害時などを想定し、モバイルWi-Fiルーターやスマートフォンのテザリングといった代替の通信手段を準備しておくことが重要です。
特に、決算期や給与計算の締め日といった業務が集中する時期の通信トラブルは影響が大きいため、事前の対策が求められます。
注意点2:カスタマイズの自由度はオンプレミス版より低い
奉行クラウドは多くの企業が利用できるよう標準化された機能を提供しており、幅広い業務に対応できます。
奉行クラウドでは、仕訳伝票の申請・承認や、証憑ごとに異なる収集プロセスに対応しています。また、「オリジナル帳票 for 勘定奉行クラウド」を利用することで、会計データに加えて非会計情報や計算式を組み込んだ独自の帳票作成も可能です。これにより、企業独自の特殊な帳票や複雑な承認フローといった個別の要件にも柔軟に対応できます。
一方、従来のオンプレミス版(パッケージ版)は、追加開発によって柔軟なカスタマイズが可能です。
そのため、自社の業務プロセスが奉行クラウドの標準機能や拡張機能で対応できる範囲なのか、あるいは業務のやり方をシステムに合わせて見直すことができるのかを、導入前に十分に検証する必要があります。
【目的別】奉行クラウドの主要製品と料金プランを一覧比較
奉行クラウドは、会計、給与計算、販売・仕入管理、人事総務といった企業の基幹業務を幅広くカバーする製品ラインナップを展開しています。
それぞれの製品は企業の規模や業務内容に応じて複数の料金プランが設定されており、必要な機能を選択して導入することが可能です。
ここでは、各業務領域の課題解決に貢献する主要な製品の機能概要と料金体系について、目的別に解説します。
会計業務を効率化する「勘定奉行クラウド」の機能と料金
「勘定奉行クラウド」は、日々の伝票入力から試算表、決算書作成まで、会計業務全般をデジタル化する製品です。
銀行の入出金明細やクレジットカードの利用履歴データを自動で取り込み、AIが勘定科目を推測して仕訳を自動起票する機能により、手入力の手間を大幅に削減します。
これにより、月次決算の早期化を実現し、経営状況のリアルタイムな可視化を支援します。
料金プランは企業の規模や必要な機能に応じて、iJシステム、iAシステム、iBシステムなどが用意されており、月額料金制で利用できます。
給与計算を自動化する「給与奉行クラウド」の機能と料金
給与奉行クラウドは、毎月の給与計算から賞与計算、社会保険手続き、年末調整まで、複雑な給与関連業務を自動化するシステムです。
勤怠管理システムと連携して労働時間を自動で取り込んだり、Web給与明細を発行してペーパーレス化を推進したりすることが可能です。
法改正にも自動で対応するため、常に正しい料率で社会保険料などを計算できます。
料金は、主に管理する従業員数や利用する機能によって変動し、企業の成長に合わせて柔軟にプランを変更できます。

社労士 小栗の
アドバイス
「給与奉行クラウド」は、労働基準法や社会保険関連法規の改正に自動で対応するため、担当者の知識不足による計算ミスや法令違反のリスクを軽減できます。これにより、給与計算業務の正確性が向上し、従業員からの信頼維持にもつながります。
販売・仕入管理を円滑にする「商奉行・蔵奉行クラウド」の機能と料金
「商奉行クラウド」は見積書作成、受注、売上計上、請求書発行、入金管理までの一連の販売管理プロセスを効率化します。
一方、「蔵奉行クラウド」は発注、仕入計上、支払管理、在庫管理といった購買・在庫管理業務を支援します。
この二つの製品を連携させることで、販売情報と在庫情報がリアルタイムに同期され、欠品による販売機会の損失や過剰在庫のリスクを低減します。
料金プランは、利用ユーザー数や管理するデータ量に応じた体系となっています。
人事・総務手続きをペーパーレス化する「総務人事奉行クラウド」の機能と料金
「総務人事奉行クラウド」は、従業員の入退社手続きや住所変更、扶養家族の異動届、各種証明書の発行申請といった人事・総務関連の手続きを電子化する製品です。
従業員はスマートフォンやPCから直接申請でき、承認ワークフローもシステム上で完結します。
これにより、紙の書類を回収・配布する手間や、手作業での情報入力ミスがなくなります。
従業員情報を一元管理することで、人事データの戦略的な活用も可能になります。
料金は主に管理対象となる従業員数に応じて設定されています。
失敗しない!奉行クラウドの導入を成功させる3つのステップ
奉行クラウドの導入効果を最大限に引き出すためには、事前の準備と計画的な進行が不可欠です。
単にシステムを導入するだけでは、かえって業務が混乱する可能性もあります。
自社の現状を正しく把握し、明確な目的を持って導入プロジェクトを進めることが成功の鍵となります。
ここでは、導入で失敗しないための具体的な3つのステップを紹介し、それぞれの段階で押さえるべきポイントを解説します。
ステップ1:現状の業務課題と導入目的を明確にする
まず最初に行うべきは、現状の業務プロセスを可視化し、どこに課題があるのかを具体的に洗い出すことです。
毎月の請求書発行に時間がかかりすぎる、経費精算が紙ベースで非効率、テレワークに対応できないなど、具体的な問題をリストアップします。
その上で、奉行クラウドを導入して何を解決したいのか、どのような状態を目指すのかという導入目的を明確に設定します。
月次決算を3営業日短縮する、ペーパーレス化率を80%にするなど、可能な限り定量的で具体的な目標を立てることが重要です。
ステップ2:自社に必要な機能とライセンス数を見極める
明確になった課題と目的に基づき、奉行クラウドのどの製品が必要かを検討します。
例えば、経理業務の効率化が目的なら「勘定奉行クラウド」、給与計算の負担軽減なら「給与奉行クラウド」が候補となります。
さらに、各製品には機能レベルに応じた複数のプランがあるため、自社の業務要件を満たすのはどのプランかを慎重に選定します。
同時に、システムを利用する従業員の人数を正確に把握し、無駄のないライセンス数を決定します。
会計事務所と連携する場合は、専門家ライセンスの活用も視野に入れます。
ステップ3:データ移行や初期設定の導入支援サービスを検討する
システムの導入でつまずきやすいのが、既存システムからのデータ移行と、自社の運用に合わせた初期設定です。
特に、勘定科目や取引先マスター、社員情報などのデータを新しいシステムに正しく移行する作業は専門的な知識を要します。
自社だけで対応するのが難しい場合は、OBCの認定販売パートナーが提供する導入支援サービスの利用を検討するのが賢明です。
専門家のサポートを受けることで、スムーズなデータ移行と最適な初期設定が可能になり、導入後のシステム定着を円滑に進めることができます。

社労士 小栗の
アドバイス
「総務人事奉行クラウド」は、従業員情報の管理や各種手続きの電子化を支援します。入社時の社会保険手続きや年末調整のペーパーレス化を進めることで、担当者の業務負担を大幅に削減できるだけでなく、情報の一元管理によりコンプライアンス強化にもつながります。
奉行クラウド導入Sに関するよくある質問
奉行クラウドの導入を具体的に検討し始めると、費用や期間、セキュリティなど、様々な疑問点が生じます。
特に初めてクラウド型の業務システムを導入する企業にとっては、不安な点も多いかもしれません。
ここでは、導入を検討している多くの担当者から寄せられる、代表的な質問とその回答をまとめました。
導入前の最終確認として、ぜひ参考にしてください。
Q. 導入までにかかる期間はどのくらいですか?
導入にかかる期間は、導入する製品の数や企業の規模、データ移行作業の有無などによって変動します。
例えば、勘定奉行クラウド単体を最小限の設定で利用開始する場合、契約から1ヶ月程度で本稼働できるケースもあります。
一方で、複数の製品を導入し、既存システムからの詳細なデータ移行や、複雑な業務フローに合わせた設定を行う場合は、要件定義から本稼働まで3ヶ月以上を要することも珍しくありません。
自社の具体的な導入スケジュールについては、販売パートナーと相談の上で計画を立てることが推奨されます。
Q. 初期費用や月額料金以外に追加費用はかかりますか?
奉行クラウドの料金体系は、初期費用と月額(または年額)のライセンス利用料が基本となります。
これには、システムの利用料、保守サポート、法改正対応のアップデート費用などが含まれています。
ただし、標準機能にはない特定の業務に対応するためのオプション機能を追加する場合や、利用するユーザー数を増やす際には、別途追加費用が発生します。
また、初期設定や操作指導などを販売パートナーに依頼する場合は、その導入支援サービスに対する費用がライセンス料とは別に必要です。
Q. 今使っているシステムからデータは移行できますか?
現在使用している会計ソフトや給与計算ソフト、Excelなどで管理しているデータは、多くの場合、奉行クラウドへ移行することが可能です。
具体的には、取引先マスターや商品マスター、社員情報、勘定科目といったマスターデータや、期首時点での売掛金・買掛金残高などをCSV形式のファイルで出力し、奉行クラウドの指定フォーマットに合わせて取り込みます。
ただし、過去のすべての仕訳データや給与明細といった履歴データの完全な移行は困難な場合が多いため、どの範囲のデータを移行するかは事前に検討が必要です。
Q. セキュリティ対策は万全ですか?
奉行クラウドは、マイクロソフト社が提供する堅牢なクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」上で運用されており、世界最高水準のセキュリティ対策が施されています。
データセンターは厳重な物理的セキュリティで保護され、通信はすべて暗号化されます。
また、24時間365日の監視体制や不正侵入防止システム(IPS/IDS)、ファイアウォールなど、多層的な防御によって企業の重要なデータを保護しています。
SOC報告書など第三者機関による評価も取得しており、自社でサーバーを管理するよりも安全な環境を確保できます。
まとめ
奉行クラウドは、サーバー管理の手間やコストを削減しつつ、場所を選ばない柔軟な業務環境を実現するクラウドサービスです。
法改正への自動対応や専門家との連携機能は、バックオフィス部門の生産性向上に大きく貢献します。
導入を成功させるためには、自社の業務課題と導入目的を明確にし、それに合った製品とプランを選定することが不可欠です。
必要に応じて専門の導入支援パートナーを活用し、計画的に移行を進めることで、その効果を最大限に引き出すことができます。