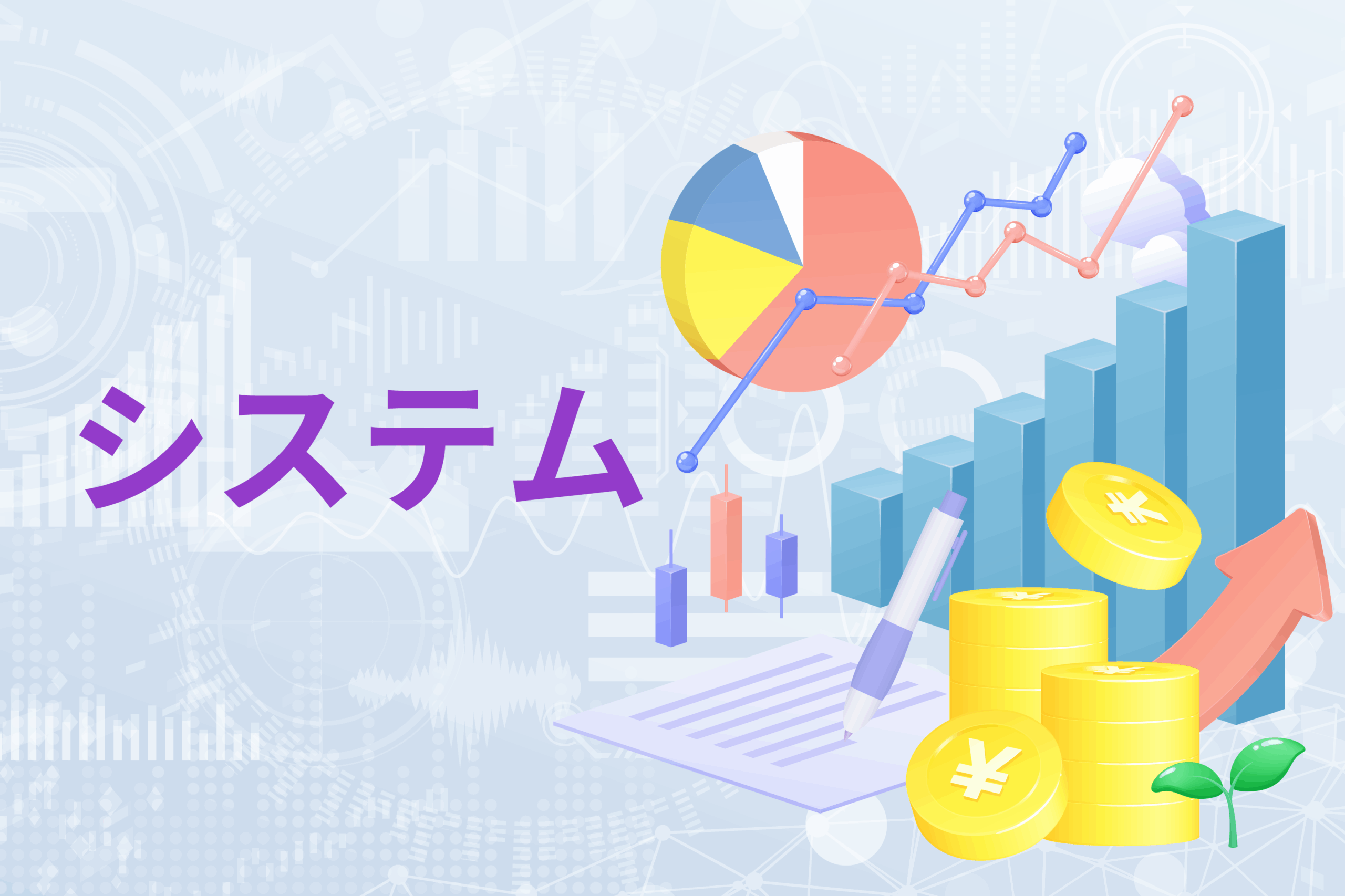勤怠管理と給与計算を連携するクラウドシステム|一括管理で業務効率化
勤怠管理と給与計算は密接に関連する業務ですが、個別に管理されていると非効率やミスが生じやすくなります。これらの課題を解決するのが、勤怠管理と給与計算を連携させるクラウドシステムの導入です。
勤怠データを給与計算へ自動で反映させることで、手作業による転記ミスや計算漏れを防ぎ、業務を一括で管理できます。
本記事では、システム連携によって得られるメリットや、自社に最適なシステムの選び方について解説します。
この記事の監修

日本ペイロール株式会社
これまで給与計算の部門でマネージャー職を担当。チームメンバーとともに常時顧問先350社以上の業務支援を行ってきた。加えて、chatworkやzoomを介し、労務のお悩み解決を迅速・きめ細やかにフォローアップ。
現在はその経験をいかして、社会保険労務士法人とうかいグループの採用・人材教育など、組織の成長に向けた人づくりを専任で担当。そのほかメディア、外部・内部のセミナー等で、スポットワーカーや社会保険の適用拡大など変わる人事労務の情報について広く発信している。
主な出演メディア
社会保険労務士 小栗多喜子のプロフィール紹介はこちら
https://www.tokai-sr.jp/staff/oguri
取材・寄稿のご相談はこちらから
勤怠管理と給与計算、こんな課題を抱えていませんか?
多くの企業では、タイムカードやエクセルを用いた手作業による勤怠管理や給与計算に課題を抱えています。
毎月の煩雑な集計作業や、法改正への対応に追われ、担当者の負担が増大しているケースは少なくありません。
これらの課題解決のためにアウトソーシングを検討する企業もありますが、まずは自社の業務プロセスを見直し、システム化によって解決できる部分がないかを確認することが重要です。
以下の項目に心当たりがあれば、システム導入が有効な解決策となる可能性があります。
タイムカードの集計と給与システムへの手入力に時間がかかる
紙のタイムカードやエクセルで勤怠管理を行っている場合、従業員一人ひとりの労働時間、時間外労働、休日出勤、深夜労働などを手作業で集計する必要があります。この作業は非常に煩雑で、特に月末の締め日には業務が集中しがちです。
さらに、集計した勤怠データを給与計算システムへ手入力する転記作業も発生します。この二重の手間は担当者にとって大きな負担となり、多くの時間を費やす原因となります。結果として、本来注力すべき他のコア業務に時間を割けなくなり、残業の発生にもつながってしまいます。
締め日になると特定の担当者に業務が集中してしまう
勤怠管理から給与計算に至る一連のプロセスは、専門的な知識が求められるため、業務が特定の担当者に集中する「属人化」が起こりやすい傾向にあります。
特に月末月初などの締め日には、勤怠データの集計から各種手当や社会保険料の計算まで、膨大な作業がその担当者にのしかかります。このような状況では、担当者が急に休暇を取得したり、退職してしまったりした場合に業務が滞るリスクが高まります。
また、業務プロセスがブラックボックス化しやすく、他の従業員への引き継ぎが困難になるという問題も内包しています。
計算ミスや入力漏れによる修正作業が頻繁に発生する
手作業による勤怠データの集計や給与システムへの転記では、どれだけ慎重に作業を行っても、計算ミスや入力漏れといった人為的ミスを完全に防ぐことは困難です。
特に、残業時間の割増賃金率の適用や各種控除額の計算など、複雑な処理が絡むほどミスの発生確率は高まります。
一度ミスが発覚すると、給与の再計算、差額の支払い、関係各所への連絡といった多くの修正作業が必要になります。
これらの手戻りは担当者の業務負荷を増大させるだけでなく、従業員の生活に直結する給与の支払いに関するミスは、会社と従業員との間の信頼関係を損なう要因になりかねません。

社労士 小栗の
アドバイス
給与計算業務の「属人化」は、担当者の急な退職や異動による引き継ぎリスクを高くします。勤怠管理と給与計算を連携させるシステムを導入すれば、業務プロセスが標準化・可視化されるため、引き継ぎがスムーズになり、担当者個人に依存しない安定した業務運営が実現します。
勤怠管理と給与計算のシステム連携で得られる4つのメリット
勤怠管理と給与計算のシステムを連携させることは、単なる作業時間の短縮にとどまらない多くのメリットをもたらします。
勤怠データを自動で連携させることで、給与計算の正確性が向上し、担当者の負担を大幅に軽減します。
さらに、有給休暇の管理から給与明細の発行、年末調整といった関連業務まで効率化が進みます。
法改正への自動対応やペーパーレス化によるコスト削減も実現でき、企業全体の生産性向上に貢献します。
勤怠データを自動で取り込み給与計算のミスを防止
勤怠管理システムで記録された従業員の出退勤時刻、残業時間、休暇取得状況などの勤怠データは、給与計算システムへ自動で取り込まれます。
この自動連携により、これまで手作業で行っていたデータの転記が一切不要となり、入力ミスや転記漏れといった人為的なエラーを根本的に排除することが可能です。
複雑な割増賃金の計算や深夜労働、休日出勤といった各種手当の算出も、事前に設定した就業規則に基づいてシステムが自動的に行うため、計算ミスが大幅に減少します。
これにより給与計算の正確性が飛躍的に向上し、従業員からの信頼を得ることにもつながります。
面倒な集計・入力作業を自動化し業務を大幅に効率化
システムの導入により、月末の締め日に集中していたタイムカードの回収、エクセルへの入力、労働時間の集計といった一連の作業がすべて自動化されます。
従業員が打刻した勤怠データはリアルタイムでシステムに蓄積され、総労働時間や残業時間が自動で算出されるため、担当者は面倒な集計作業から解放されます。
この自動化は、勤怠締めから給与計算、給与明細の発行に至るまでのリードタイムを大幅に短縮します。
その結果、担当者は時間に余裕を持つことができ、創出された時間を人事評価制度の策定や労務環境の改善といった、より付加価値の高い戦略的な業務に充てられるようになります。
法改正の内容が自動でアップデートされ対応漏れを防ぐ
労働基準法や社会保険料率、最低賃金などは頻繁に法改正が行われます。
担当者は常に最新の情報を収集し、給与計算のロジックを正確に更新し続けなければなりません。
クラウド型の勤怠管理・給与計算システムは、法改正が行われるとベンダー側でシステムが自動的にアップデートされるため、担当者が自ら情報を追いかけて対応する必要がなくなります。
割増賃金率の変更や新たな控除項目の追加なども、常に最新の法令に準拠した状態で給与計算が行えるため、法改正への対応漏れや知識不足による計算ミスといったリスクを効果的に回避できます。
これにより、コンプライアンスを遵守した適切な労務管理が実現します。
ペーパーレス化の推進で管理コストの削減につながる
勤怠管理システムの導入は、紙のタイムカードや出勤簿を不要にします。
同様に、給与計算システムと連携することで、給与明細や源泉徴収票なども電子化し、従業員へオンラインで配布することが可能になります。
これにより、用紙代、印刷代、郵送費といった直接的なコストを削減できます。
さらに、書類のファイリングや保管スペースの確保、過去の書類を探す手間といった間接的な管理コストも大幅に削減されます。
書類の紛失リスクが低減し、必要な情報をデータとしていつでも迅速に検索・確認できるようになるため、管理業務全体の効率も向上します。

社労士 小栗の
アドバイス
給与計算システムを導入する最大のメリットは、給与や残業代の計算を自動化することで、労働基準法や社会保険関連法規の知識不足によるミスを防げる点です。これにより、従業員の賃金に関するトラブルを未然に防ぎ、企業のコンプライアンスを強化することができます。
自社に最適なシステムを選ぶための5つのチェックポイント
勤怠管理システムは数多く存在し、それぞれ機能や価格帯が異なります。そのため、おすすめの製品を比較する際には、自社の課題や運用に合ったシステムを見極めることが重要です。
弥生給与などの既存ソフトとの連携性や、アルバイトを含む多様な雇用形態への対応力は必須の確認項目です。
無料トライアルを活用して、従業員が使うアプリの操作性を試すことも有効です。以下の5つのチェックポイントを参考に、自社にとって最適なシステムを選定してください。
現在利用している給与計算ソフトと連携できるか確認する
すでに特定の給与計算ソフトを導入している場合、新しく導入する勤怠管理システムがそのソフトとスムーズに連携できるかの確認は、最も重要なポイントです。
システム間の連携ができないと、勤怠データを一度CSV形式などで出力し、手動で加工してから給与計算ソフトに取り込むといった余分な作業が発生し、業務効率化の効果が半減してしまいます。
主要な給与計算ソフトの多くは、連携可能な勤怠管理システムを公式サイトなどで公開しています。
導入を検討しているシステムの連携実績や、データ形式の互換性を事前に必ずチェックし、勤怠データを自動で取り込めるかどうかを見極めることが選定の失敗を防ぐ鍵となります。
複雑な就業規則や多様な雇用形態に対応しているか
企業ごと就業規則は異なり、フレックスタイム制、変形労働時間制、みなし労働時間制など、独自の勤務体系を設けている場合があります。
また、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトといった複数の雇用形態の従業員が在籍していることも珍しくありません。
システム選定時には、自社の複雑な就業規則や、雇用形態ごとに異なる勤務シフト、時給計算、残業代の割増率設定などに柔軟に対応できるかを確認する必要があります。
特に、複数の拠点がある場合は、事業所ごとに異なるルールを設定できる機能も重要です。
無料トライアル期間などを利用して、自社の勤務パターンを実際にシステム上で設定し、問題なく運用できるか試すことが望ましいです。
全従業員が迷わず使えるシンプルな操作性か
勤怠管理システムは、労務管理者だけでなく、全従業員が日常的に利用するツールです。そのため、ITリテラシーにかかわらず、誰もが直感的に操作できる分かりやすさが求められます。
打刻方法が複雑であったり、休暇申請のプロセスが分かりにくかったりすると、従業員からの問い合わせが増加し、かえって管理者の負担が増えることになりかねません。PC操作に不慣れな従業員でも迷わず使えるか、スマートフォンやタブレットからの打刻や申請に対応しているかといった点も重要な確認項目です。
管理画面においても、メニュー構成が明快で、勤怠状況の確認やデータの修正、各種申請の承認などがスムーズに行えるかどうかを、デモやトライアルで確かめるべきです。
トラブル発生時に頼れるサポート体制が整っているか
システムの導入時や日々の運用において、操作方法の不明点や設定の誤り、予期せぬエラーといったトラブルが発生する可能性は常にあります。
特に給与計算に関連するシステムの場合、問題が迅速に解決されなければ業務に大きな支障をきたします。そのため、提供元ベンダーのサポート体制が充実しているかは、非常に重要な選定ポイントです。
サポートの対応時間(平日日中のみか、夜間や休日も対応可能か)、問い合わせ方法(電話、メール、チャットなど)、そしてレスポンスの速さを事前に確認しておく必要があります。
初期設定の代行サービスや、法改正に関する情報提供、運用を支援するコンサルティングの有無なども含めて検討すると、より安心してシステムを利用できます。
会社の規模や成長に合わせて拡張できるか
企業は成長とともに、従業員数が増加したり、新たな事業所が開設されたり、多様な雇用形態が生まれたりします。
システムを選ぶ際には、現在の企業規模に最適であることと同時に、将来的な事業拡大にも柔軟に対応できる拡張性(スケーラビリティ)を備えているかを確認することが重要です。
具体的には、登録できる従業員数の上限、追加可能な機能の範囲、人事評価やタレントマネジメントといった他の人事関連システムとの連携の可能性などをチェックしておきます。
将来的にシステムを乗り換えることになれば、データの移行や再設定に多大なコストと手間を要するため、長期的な視点で、会社の成長に合わせてプランや機能を追加できるシステムを選択することが望ましいです。
勤怠管理・給与計算システムの主な連携タイプ
勤怠管理と給与計算を連携させるシステムは、主に「一体型」「連携型」「ERP型」の3つのタイプに分類されます。
それぞれのタイプには特徴や機能に違いがあるため、自社の状況に合わせて選択することが重要です。
例えば、freee人事労務やジョブカン給与計算のように勤怠から労務までを網羅するサービスもあれば、既存のシステムと柔軟に組み合わせる製品もあります。
また、kintoneのようなプラットフォーム上で自社に必要な業務アプリを構築し、連携させる方法も考えられます。
勤怠から給与計算まで一元管理できる「一体型」システム
一体型システムは、勤怠管理、給与計算、年末調整、社会保険手続きといった人事労務関連の機能を一つのパッケージで提供するタイプです。
最大のメリットは、最初から全ての機能がシームレスに連携するように設計されているため、データ連携のための複雑な設定が不要で、スムーズに導入できる点です。
操作画面やインターフェースが統一されており、直感的に扱いやすいことも特徴です。データが一元管理されるため、情報の整合性が保ちやすく、管理も容易になります。
一方で、機能がパッケージ化されているため、自社には不要な機能が含まれていたり、特定の業務に必要な細かい機能が不足していたりする可能性があります。そのため、導入前に機能要件を十分に確認することが求められます。
必要な機能を柔軟に組み合わせられる「連携型」システム
連携型システムは、勤怠管理と給与計算など、それぞれ独立した専門システムをAPIやCSVファイルなどを介して連携させて利用するタイプです。
このタイプの最大のメリットは、各分野で評価の高い、自社のニーズに最も合致したシステムを自由に選択して組み合わせられる点にあります。
例えば、勤怠管理は複雑なシフトに対応できる高機能なシステムを選び、給与計算は長年使い慣れた会計ソフトと連携させる、といった柔軟な構成が可能です。
必要な機能だけを選んで導入できるため、コストを最適化しやすいという利点もあります。
ただし、異なるベンダーの製品を組み合わせるため、導入時にデータ連携のための初期設定が必要となる点や、システム間で問題が発生した際に原因の切り分けが複雑になる場合がある点には注意が必要です。
他の基幹業務もまとめて管理できる「ERP型」システム
ERP(Enterprise Resource Planning)型システムは、勤怠管理や給与計算といった人事領域だけでなく、会計、販売、生産管理など、企業のあらゆる基幹業務を統合的に管理するための大規模なシステムです。
最大の強みは、勤怠データや人件費といった情報を、企業の経営情報や会計情報とリアルタイムで連携できる点にあります。これにより、企業全体のデータを一元管理し、経営状況を正確に可視化することで、迅速な意思決定を支援します。
人事情報と勤怠・給与データが完全に紐づいているため、適正な人員配置の検討や部門ごとの人件費分析など、より戦略的な人事施策にも活用できます。
ただし、非常に高機能である分、導入・運用コストが高額になる傾向があり、主に中堅・大企業向けの選択肢となります。

社労士 小栗の
アドバイス
給与計算システムと勤怠管理システムを連携させる際は、自社の就業規則や給与規程にシステムがどこまで対応できるか、事前に確認することが非常に重要です。システムに合わせるために規程を変更する必要がある場合は、従業員への説明や労使協定の再締結も検討しましょう。
まとめ
勤怠管理と給与計算を手作業で行うことは、多くの時間を要するだけでなく、人為的なミスの発生源となります。
これらの業務をシステムで連携させることで、勤怠データの自動取り込みが実現し、計算ミスを防止するとともに業務の大幅な効率化が可能です。
加えて、法改正への自動アップデートやペーパーレス化によるコスト削減といった副次的な効果も期待できます。
システムを選定する際は、既存の給与計算ソフトとの連携性、自社の就業規則への対応力、従業員と管理者双方にとっての操作性、サポート体制、そして将来の事業拡大を見越した拡張性を総合的に評価することが不可欠です。
一体型、連携型、ERP型といったシステムの種類ごとの特徴を理解し、自社の規模や課題に最も適した製品を選択することが、労務管理全体の質を向上させます。